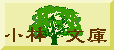

連休前進行を昨夜終わらせて、少し余裕ができました。
雑誌や本を作る側からすると落丁、乱丁、誤植というのは胸が痛むものです。
私も大ミスを何度もやりました。見開きが左右逆だとか……(恥)。
エラー切手的な価値もわからないではないですが。つらいです。
上のURLで「『新青年』趣味」が取り上げられています。
インタビュアーはお馴染み南陀楼綾繁さんです。綾繁さんが旧知の編集者だっ
たというのをインタビュー直前に知って、驚きました。
引き続き、海野忌講演会の宣伝もしています。奮ってご参加ください。
落丁あるいは乱丁の雑誌を最近みかけませんが、昨日、店頭で手に取り、そのまま購入した、雑誌「SFマガジン」6月号。
見たとき、乱丁を確認していましたが、これでいい、と思い、購入してしまいました。
241ページ以後、256ページまで、上下さかさまで、製本されていました。
そう言えば、以前、手に入れた、乱丁の、雑誌「幻影城」。こちらは刷りなおされたのか、表誌の色調がことなるものでした。
意外とあるものです。
『京都出版史 明治元年ー昭和二十年』は、今でも、定価割れながらも、京都にある古書店の吉岡書店で新刊で手に入ります。戦後版も出ていますので、有用です。
講談社文庫の、『日本探偵作家論』権田萬治。黒背のほかに、橙背のものもあり、その橙背を古書店で入手。どちらも、初版です。比較してみても、訂正や加筆がないようです。値段も同じ、定価320円。
これも、先日、手にいれた、1992年の悠思社版では、細かな訂正、加筆がとくに初出誌を中心におこなわれ、さきの講談社版文庫よりは便利です。
三橋一夫さんの著書で、昭和十八年、とされる、『涙橋』。
『勇士カリガッチ博士』図書刊行会の、東雅夫さんの解説では、未見とされていましたが、その書誌が、『京都出版史 明治元年ー昭和二十年』の、昭和十八年の項にありました。
涙橋 三橋一夫 179 1.80 人文書院
これは京都の出版社です。
関西の古書店の人に訊きますと、一度あつかったことがあるらしい。あるのですね、探究のひとつとなりました。
扶桑社文庫『加田伶太郎全集』、二刷、2001.4.10、が平台に重ねられています。初版での、あの箇所がなくなり、すっきりしています。帯などは初版と同様でした。
「新青年賞」は読者が決める賞でした。
「日記賞 博文館」と印がおされたのは読者へ与えられた、何かの懸賞にあたる賞と思われます。この印がある本を、すでに2冊入手しています。
昨日は、古書店で、「世界探偵小説全集 グリーン」平林初之輔訳を入手。これにもその印が押されていました。状態は悪いながら、このシリーズ、印が押されていたのは2冊目のものです。昭和四年に発行されています。
青帯、赤帯の『吸血鬼』、両方ともあることがわかり、末永さん、Dupinさん、ありがとうございます。
この乱歩の推理文庫、書店で出れば、購入していたので、私のは赤帯だったのです。『貼雑年譜』は、異なる版が出るたびに購入していた覚えがあります。帯が破損しているものが多いです。
末永さん、第一回は、十蘭でしたか。
人気投票ということですので、小栗さんの場合も、その年に、本が出たのですから、博文館には必要な賞だったのでしょうか。
徳間ノベルス、2巻までだと思っていた、西村京太郎さんの、自選集、第三巻
がでました。「鉄道ミステリー編」です。山前さんの解説があります。名作6編が収録されています。
小栗さんは第二回受賞です。
年間人気投票なので、文学賞というわけではないのですが、小栗さんの唯一の受賞かと。
Dupin様。
「うつし世は夢」の出し直しのスバヤサから考えると、すぐに講談社は対応したのでしょうね。本体には問題がないので、再出荷分に刷りなおしたものを巻いただけだけではないでしょうか(帯にはISBNが入っているので刷りなおさなければなりません)。
ハードな乱歩マニア(私は違うのですが)は、たいてい予約購入していたでしょうから、一般的な部数としては「青帯」が多くても、マニア界では「赤帯」の方がポピュラーかと(笑)。
とっても薄いけど、乱歩マニアのDupinです。
乱歩推理文庫の「吸血鬼」がミスで赤になっているのは有名ですが、再版時なのかどうかは忘れましたが、すぐに青帯、青仮面で出し直されてました。
初版時に全て購入していて、並べるとこの巻だけが、居心地が悪かったので、それも買おうとした事があります。(結局買いませんでしたが)
そっちの方が珍しいんですか?私は赤ヴァージョンの方が珍しいのかと思っていました。
大阪圭吉さんの「秘密」が掲載されている、「新青年」昭和十五年一月号。小栗さんも『有尾人』博文館刊(昭和十五年七月)に所収されることになる短編のひとつが掲載されています。
第2回「新青年賞」を受賞したのが、前年度に掲載された「大暗黒」。受賞のコメント、「「魔境征服記」について」を小栗さんが書いています。
この「新青年賞」についての、選考をみますと、人気投票を主として意見を総合した結果、とされていました。
帯があらたにまかれることもあるのですね、それにしても、青帯はあらたにつくられたのでしょうか、この青帯版は乱歩推理文庫に並べたくなります。
おりしも、喜国さんの本棚が「ふるほん横丁」の第三回目に、紹介されています。ここには、乱歩の推理文庫の書影はありませんが、函付きの、夢野久作、佐左木俊郎、森下雨村などの新潮社の書き下ろし作品があり、また、「八つ墓村」角川文庫の書影は、とてもいいです、すごさがあります。
末永さん、春陽堂の資料があれば、宝の山ですが、それでも、社長さんにあわれて話されたということ、これはうらやましくなります。
昨日,春陽堂の荒井社長にお目にかかったのでお伺いしたところ,戦中の資料は残っていないとのことでした.というのは,戦後,倉庫が火災に遭ったために多くの資料が失われたから,とのことでした.残念.
岩堀様.
そういえば,春陽文庫収録時に「コント」という無粋なタイトルになってしまったようで.春秋社版では「とりどり屑篭の千代紙」という典雅なタイトルがついておりました.私はPCの雑多な文書を入れるフォルダに「とりどり屑篭の千代紙」をもじった名前を付けております.ミーハーです(笑).
あの殺人方法は後世に残るバカなものです.流行りの「バカミス」?
「こくり」問題は文章で見たことはないのですが,ある古い人にうかがったことがあります.信憑性はあるようなないような.私は疑問を持っていたのですが,「こっくりはん」でちょっとぐらついたりしています.
桜様.
オーナー様はここらへんは押さえていらっしゃるのでしょうか.
さっき,ウチのを見たら昭和14年9月発行の第11号「尋ね人をする女」っていうのがありました.読んでませんが「美しき応召ロマンス」と編集後記にあります.
『ロック』問題,今週は連休進行でゴタゴタしているので落ち着いてさがしてみます.
日下さんの『久生十蘭集』購入.「刺客」(と都筑エッセイ)が手軽に読めるようになったのはいいことですね.『ハムレット』より好きだったりして(『ハムレット』は登場人物の年齢など細かいところが納得できないので).
十蘭は改稿の過程が面白いので,『湖畔』の全バージョンが読めるような完全版全集が出てくれるとありがたいのですが.
五年前に、Tさんが出されていた「大阪圭吉研究資料集」第1集にある作品リスト。
昭和17年
17・8 20 ソロモン海の鬼鷲 戦線文庫十月号 五十円
の、鬼鷲、とは何だろうと、いう記憶がありました。先頃入手の、その「戦線文庫」第四十八号、昭和十七年十月発行。9ページの短編。該当のは
海鷲小説 ソロモン海の羽ばた(手へんに専)き 大阪圭吉 木村俊徳画
でした。このあたりの資料は手に入れるしかないのですね。
末永さん、「ロック」問題。鮎川さんと編集長の山崎徹也さんは知り合いのようでしたので、どのようなことであったのか、知りたくなります。
末永様
参りました。「合俥夢権妻殺し」は沖積舎『小栗虫太郎ワンダーランド』で
したか。
桃源社版は本棚から全部出して目次を見たのですが、ワンダーランドは一段
下のしかも反対側にあったので目がいきませんでした。もっとも、目次を見
ても「コント」ですから気がつかなかったでしょうね。特集雑誌的なものは
拾い読みなもので、やはり未読でした。早速今日5分くらいで(^o^)読みま
した。トリックが小栗的かつ爆笑もので案外面白かったです。
>最後に小栗さんのことを「こっくりはん」と呼びますが、これって
>《「小栗」を「「こくり」と読む説》の根拠になっているのでしょうか。
そういう説があるとは知りませんでしたが、難しいところですね。
少なくとも、「こくり」と読むのが正しいのではという主張の拠り所の
一つにはなるかもしれませんね。「小倉」でも、「こくら」、「おぐら」
両方ありますね。
鮎川哲也氏がエッセイに書かれていたのではなかったでしょうか.
うろ覚えなのですが,例えば『幻影城』なんかで.
新聞沙汰になったというようなことだったと記憶しています.もしかしたら別の話(『宝石』?)かもしれませんが.
須川様.
こちらこそ.
蘭郁次郎全集(?),もっと話題になってもいいと思っています.「読めるだけでいい派」には,あの価格は魅力でしょう.
オーナー様はよくご存じだと思いますが,大阪圭吉は蘭さんよりはるかにテキスト収集が難しいので,大変なご苦労だと思いますが何とかやってほしいものです.
桜様.
新刊書店で購入した本に,別の帯が掛かっていることも何度か経験しています.
いろいろな事情があって,新刊書店の店員さんが掛け替えたものだったようです.それで結果的に本体と違う帯が掛かった本を2冊持っています.いずれも全集ものの1冊でした.
赤い帯が目立ちますね、『吸血鬼』。
須川さんが言われた青帯版も探さなくてはなりません、すでに揃いはありますが、これは気にして、古書店の棚を見ることにします。ありがとうございます。
やよいさん、書き忘れましたが、「ロック」、四巻四号以後は、何度もその期間に、再録をくりかえして、表紙張り替えで,中身は同じものです。
「IN POCKET」2001・4月号。喜国さんの書斎がイラストで紹介されています。「貼雑年譜」復刻版、2冊、そして「笑う肉仮面」も左端にのぞいていました。東京創元社の校正用原稿、その中身が気になります。
末永さん(御無沙汰してます)
確かに活字に比べると、①通勤途上や、寝ながらさらにはトイレで読む自由度
に欠ける(僕の主要な読書時間) ②触覚や嗅覚に訴えるものがない・・
といった弱点はあるのですが、何しろコストパフォーマンスが良いです。
蘭郁二郎作品100篇以上が再録され\10,000!(僕は前売り\8,000でした)
何部出たのか知りませんし、採算がどうか知りませんが印刷ではこうは行き
ませんよね。
更に感動すべきは7大付録付(直筆原稿、ドラマ脚本、刊行本、遺品の書影、
書誌・・)という事です。毀誉褒貶はあるでしょうが、偉業と言って良いと
思いました。
是非PDA(僕はソニーのクリエ)に載るようにしてほしい、次は大阪圭吉を
やって欲しいと無理を言っておきました。
桜さん
「吸血鬼」青帯版は「自負のアリバイ」の帯、「教養文庫小栗選集4,5巻」
の帯 と違って実在するのではないでしょうか?
やよいさん、懸賞の行方については知りたいですね、その後、3回目が掲載されていないところを見ますと、横溝さんの小説と同じように中断したのでしょうか。
実は、「ロック」、その後も刊行されていたのです、昭和二四年では、五冊、四巻五号まであります。該当の、三号は、「夏の別冊」ですから、ここには掲載されていないようです。
おりしも、懸賞未払いが起こり、新聞に(この11月です)とりあげられたので、推定ですが、島田さんの懸賞も、そのまま、発表されなかったように考えられます。
昭和二五年には、四冊も刊行されています。
この五巻四号が終刊と思われます。いずれの号にも、島田さんの小説はありませんでしたが、九鬼さんの小説は掲載されています。
どうも、ご無沙汰していました。
某作家の作品リストの作成を相変わらず続けているのですが、一つ疑問が発生しました。雑誌に詳しい方が集うこちらなら助けて頂けるのではないかとお尋ねします。
「ロック」のS24.2月号と5月号に『災厄の黄昏』という島田一男の作品が掲載されています。実はこれ、当時としては破格の一等賞金1万円という懸賞問題でした。この2号が問題編で続く6月号に当選者発表とありましたが、6月号にはざっと見渡す限りではその記事がありません。「ロック」はこの号が最終号だったと思うのですが、果たして回答はどうなったのでしょう。どなたかご存知ありませんか?
番号順に正しく並べられているかを調べますと、同じ番号が、ふたつ。帯の色がことなりますが、他の巻の帯がまかれていました。
いつ手に入れたのか(これがミスでした)、おそらく、これは古書店で見つけたものです。帯を替える人がいるのですね。
また、もう1つ揃えようとした巻の方を見ますと、同じ帯が二つ巻かれた巻もありました。
このところ、古書店で、帯の無い、二刷を求めていますので、乱歩推理文庫をみなおすことになりました。
須川さん、末永さんのかかれておられますように、『吸血鬼』(青帯の巻のなかの赤帯)の、赤帯が目だっています。
須川さん、私も、『吸血鬼』(青帯)については聞いたことがありますが、これは、ある種の、無いものを探す話のひとつでしょうか、確かめたいですね、この掲示板で。
させていただきます。
先日お知らせした海野十三の会の講演会の詳細が上記のホームページにアップされていますので、みなさまご覧ください。
会場が四国なので、東日本の方は参加しにくいかと思いますが、
皆様どうぞよろしく。
調べてみたのですが、変なのは『吸血鬼』(青帯の巻のなかの赤帯)だけでした。「赤帯の巻のなかの緑の帯」っていうのはどの巻のことなのでしょうか。
それにしても、ずっとあのまま並べられるかと思うと、あの文庫の担当者に同情してしまいます。
岩堀様。
「合俥夢権妻殺し」は沖積舎の『小栗虫太郎ワンダーランド』と春陽文庫の『完全犯罪』に収録されています。
楽屋オチのたわいない話ですが、私はいろいろな「ヒント」が詰まっている作品だと思っています。『ぷろふいる』の堀場老人も登場する珍作として、単純に楽しめばいいようなものではありますが。つい、深読みしてしまいます。
須川様。
以前の書き込みのレスですが、蘭郁二郎はいかがでしたか?
電子本がどれだけ普及するか、大変に興味があります。私はやはり紙の本にこだわってしまうのですが、「次善の策」として電子本もやむを得ないかと考えています。
本日、長谷川卓也氏に、かつて氏が勤務していた東京新聞についてのお話を伺いました。いろいろな中絶小説の中絶理由についてなど大変面白かったのですが、十蘭の中絶作『をがむ』の中絶は、やはり終戦直前(昭和20年夏)という時期だったので小説の掲載が続行できなかったのが原因だったようです。
私は数年前、国会図書館読んだのですが、残念なことに欠号があるため完全には読めませんでした。一種の現地小説で、当局の忌避に触れるものではないのですから、内容に問題があったとは思えません。私の記憶では、戦後に改作されていないタイプのストーリーだったので、大変貴重だと思います。完結していれば、十蘭の数少ない戦中の長編だったので残念です。
桜さん
赤帯の巻のなかの緑の帯というのも
あるんですか?!
「吸血鬼」青帯版は以前どこかで
書かれていたので知っていたので
すが・・
PS 「吸血鬼」青帯版、誰か譲って
ください (-_-;)
乱歩の特集、雑誌にのれば、購入することになりますが、まだ、平井さんの本、出ていないのでしょうか、これも楽しみにしています。
岩堀さん、「乱歩の時代」もありましたね。
蔵書目録を待ち望んでいますが、これはまだ作成されていないのでしょうね。
「小林文庫」のアクセス数、27万回目、先週の金曜日でしたが、初めて、キリ番というものにあたりました。午後4時過ぎでした。
末永様
>小栗のトリックを理解するのは、とうにあきらめておりまして、ただ、
>あのわけのわからないテンションの高さに身をゆだねている
私も同様です。小栗の作品は「よくわからないが面白い」だと
思います。本格物に限らず、人外魔境の「水棲人」なども水の底で
どうやって生きているのか、説明はありますが、???というところが
面白いですね。
>「合俥夢権妻殺し」のギャグが、・・・
私は未読です。これは桃源社版には載っていない作品ですね?
桜様
乱歩の特集とは少し違いますが、別冊太陽で「乱歩の時代」というのが
ありますね(1995-1発行)。昭和初期のエロ・グロ・ナンセンス
の気分がよくわかります。
| Powered by T-Note Ver.3.20 |