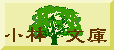

ごぶさたしています。はじめて書き込みをさせていただいてから、
ずいぶん経ってしまいました。その間、熊谷市郎さんの出版リスト
では、皆さまからずいぶん多くの情報をよせていただき、また
このような公開調査をしていただいたオーナー様はじめ、
感謝しております。
私のほうはと言いますと、熊谷さんのインタビューのテープ起こしを、
ようやく終えました。やはり文字に起こしてみると話が整理されて
見えてくるもので、ずいぶんたくさんの事実が盛りこまれていることに
改めて気づきました(拙文での誤記もあり)。内容を早くお知らせしたい
のですが、とりあえず近い日に、実際にインタビューにあたられたお二方に
お会いして、言葉の不明瞭な部分を判聞したり、どう編集するかを相談する
予定です。インタビュアーのお二人には、この熊谷市郎氏インタビューの
監修者をお願いしています。テープを聞いていまして、お二人の探偵小説
に対しての熱情と博識があったからこそ、熊谷さんから多くの話が聞けた
ことです。お二人が誰なのか、皆さんもある程度ご存じではないでしょうか。
雑誌の掲載は五月半ばになる予定ですので、楽しみにしていてください。
この掲示板では熊谷さんについての情報をいろいろと寄せていただいているので、私もその後の発見をひとつ報告しようと思います。それは紀田順一郎氏の
『明治風俗故事物語』(河出文庫/昭和60年)に「Dデパート由来記」という項目があり、ふとそこを読み出したらなんとそれが熊谷さんのやっていた呉服商の由来だったのです。明治十八年の新聞記事によって書かれたそれは、呉服商のの初代にあたる熊谷市兵衛さんが、一代で「大丸市」を築きあげるサクセスストーリー。
ふつうだったら見過ごしてしまいそうな記事ですが、紀田氏は、その熊谷氏の子孫が『ぷろふいる』の発行者だったことを知っていたのでしょうか。探偵小説に詳しい紀田氏なだけに、偶然でもそこに触れているのは面白い事実です。
この由来記については私が知りえた「大丸市」の由来と相違する部分もあり、
もうすこし調べねばいけないと思います。
もうひとつご報告として、先日、熊谷さんの長女、素江さんからおハガキ
をいただきました。
「父のこと色々調べて下さって暖かい目で書いて
下さってとても嬉しく思いました」
とあり、それはいまこのHP上で皆さんが繰り広げてくださってる
熊谷さんへの再評価に対して送られる言葉でもあります。
また素江さんは
「ぜひお会いして私の記憶の中にある父の事など
お話したいと思います」
とおっしゃってくださいました。
ほんとうに近い日、お会いしてぜひ、お話をうかがいたいと思います。
>芦辺 拓 さん No.1128 03/14
>涙香で思い出しましたが、彼の訳した「怪しの物」をどこかホラーアンソロジーに
>入れてくれませんかね。
たしか「幻想文学」第18号 (1987.5.20) に抄録された作品でしたか。
読んでみて面白かったら、復刻してみたいものですね。出版人では
ないのでアンソロジーは無理ですが、青空文庫でなら私にだって。
http://www.d2.dion.ne.jp/~octa/pages2/18.html
が徳島で開催されます。毎年、海野忌に行われている講演会です。
5月12日(土)14時~16時、会場は徳島県郷土文化会館(徳島駅から徒歩5分)です。参加無料。
講師は『新青年』研究会の天野裕康(渡辺晋)氏、
演題は「海野十三と雑誌『新青年』の周辺」です。
詳しくは近日中に『新青年』研究会ホームページでも告知いたしますが、本日は速報です。どうぞ皆さん、ご参加ください。
私も行きたいのですが、いかんせん四国では……
ということで、宣伝させていただきました。>オーナー様。
海野十三の会の小西さんと電話でお話ししたのですが、昨日の地震、大変だったようですね。お見舞い申し上げます。
吉井勇さんの本が本棚にあることを思い出しました。都筑さんの本には題名がないので、違うかな、と思い、取り出しました。
『市井夜講』昭和22.3.5、新月書房
でした。こんなこともあるのですね。
発行者 西宮清 熱海市水口区上ノ山一八四七
都筑さんの本では、西宮社長、とされています
発行所 新月書房 熱海市水口区上ノ山一八四七
印刷者 川井正男
八王子市千人町三ノ五一
ということで、新月書房が熱海市にあるので、都筑さんはその当時、どこに住まわれておられたのか、疑問にのこります。
解答は、どこにあるのでしょうか。
岩堀さん、「追跡『東京パック』」はいい本でした。特に、人間の動きがとらえられており、すばらしさを感じました。25年も、ついやされたのです。
須川様
>「猟奇」傑作選のコラムだけ読了しましたが
>すごく面白かったです。僕の好きな斎藤緑雨並の
>毒で、昔の人はすごいもんだと感心しました(゚o゚)
須川さんの書きこみをみて、私も読んでみました。
全く同感、面白かったです。
「新青年は何故新進作家を優遇しないのか?甲賀三郎の百枚
ものを載せるよりも、新進作家のニ十枚ものを五編載せる方が
どの位ましかわからないのか?」なんていうのは、「新青年」と
「甲賀三郎」を変えればいつの世でも通じそうですね(^o^)
桜様
「追跡『東京パック』」読了しました。いい本ですね。両親の実家が、
下田憲一郎の出た横手の近くの湯沢ということもあって身近に感じ
ましたが、それだけでなく、あの時代を生きた有名、無名の人達の
さまざまな人生に胸を打たれました。著者の高島真さんの情熱もすば
らしいと思います。
「浅草十二階」が動いている、それが見られるなんて、フィルム上映が楽しめますね、大塚さん、情報は命と思います。
戦前、戦後のこと、その中での動きは活字よりも、映像ですね。「日本ミステリーの100年」にも、世の中の動きもかかれており、手放せません。
「日本探偵作家論」権田萬冶(講談社文庫)をひろげて、水谷準さんについての「水谷準論 黒き死の賛歌」を読んで、彼の作品では、「R夫人の横顔」「夜獣」「ある決闘」を印象深く思い出しました。
こういう時、宮澤さんの、リストをみますと、数多くのアンソロジーに採用されていることがわかります。すぐにわかるので、すばらしく、宮澤さんのリスト、とても役立ちます。
それにしても、水谷さんは生前には復刊の許可をされないこと、初めて知りました。
桜様
>定期的に上演されているのでしょうか、フィルム上演は興味あります。以前、NHK
>で、これらのフィルムのこと、とりあげていました
基本的には月単位の特集上映で明日24日が最終日になります。今回の第一弾が劇映画で、次回以降はドキュメンタリー主体になるようです。
今回は大正期の映画も上映され、簡保の宣伝映画で、意地悪で高利貸しのおじさんが、関東大震災で焼け出され、いじめてきた親戚の子供が少ない小遣いを積み立ててきた保険金でおじさんを助け、めだたしめでたしという、今では考えられない展開のものもありました。その関東大震災のシーンがリアルタイムの実写で、見ていて「浅草十二階が動いてる」と思わず声が出てしまいましたが、周囲でも嘆声がもれいました。
末永さん、ありがとうございます。よくわかります、後藤竹志さんの関与されたこと。もと、「芸林閣」の編集者でした。
水谷さんのは創元推理文庫「名作集 I」に3作あります。偶然、その前日、渡辺さんの作品とともに読みました。九七歳でしたか。
都筑道夫さんのこと、年代順にまとめますと、
昭和二一年 新月書房に勤務
6月 スバル社版「スバル」創刊 4冊刊行(後藤編集)
10月 「寄席」新月書房、創刊 2冊か(山本勝利編集)
昭和二二年 小林昌(上に草冠がつく)夫(別名)使用
6月 「川柳祭」創刊(天野仙太郎編集)
11月 「萬国」改題「スバル」創刊(萬国新報社)
?月 「幕間」創刊(間瀬寛司編集)
昭和二三年 新月書房退社
?月 「ポケット講談」創刊、青灯社(後藤編集)
昭和二四年 都筑道夫を使用
2月 「スバル」終刊
8月 「ポケット講談」の継続を確認
?月 「毎日読売」創刊、好江書房(阿部主計編集)
?月 「幕間」終刊
となり、ふとしたことから、わかりかけてきました。
私のところにも、
平山さんから
「明智小五郎年代学」
「ベイカー街年代学」
を送っていただきました。
いや、こりゃいいわ。
届いたばかりでまだぱらぱらとしか読んでませんが、
読み応えがありそうです。
この冊子の存在を知ったのはこの掲示板がきっかけです。
敷居がすっかり高くなっても(笑)ROMを続けててよかった。
7冊も出ていましたか! 島崎リストでは1冊となっておりました。
山本明氏の『カストリ雑誌研究』を読み返したのですが、この本の資料提供が島崎さんだったんですね。島崎さん以外には長谷川卓也さんほかだそうです。長谷川さんは現在はお持ちでないというお話でしたが(たしか水害かなにかに遇われたとうかがっています)。
訃報に際して、ご冥福をお祈りいたします。
渡辺啓助氏のように作品集が刊行されればと思っていた矢先でした。ご長命だったとはいえ、残念です。
桜様。
どうも、後藤氏の一連の出版社は、実質的に同じものと考えていいようですね。
雑誌ごとに(名目上の)版元を変えるというのは、いかにもあの時代にはありそうなことです。税務上の理由などが考えられますが、こういうことが後の調査を難しくしています。大変ですね。
日がかわりました。
相変わらず、古書を入手していない日が続いています。
下で述べた「萬国」が何冊出たのか、わかりませんでした。新月書房からは7冊出ているのですが、これらの中では、再刊で、牧逸馬「この太陽」上・下巻,大下宇陀児の探偵小説、城昌幸「若さま侍捕物帳」があります。
大塚さん、定期的に上演されているのでしょうか、フィルム上演は興味あります。以前、NHKで、これらのフィルムのこと、とりあげていました。
岩堀さん、私も創元推理文庫「名作集I]を手にとり、昨日読みましたが、意外と、短い話でした、展開をよみながら思い出しました。五年前に、この巻で全集は完結したのですね。
末永さん、思わぬことで、いくつかのことが明らかになりました。
都筑道夫さん(1929年,昭和4.7.6生)について少し年代を整理できます。
・新月書房(昭和二一年から昭和二三年暮まで)、最初に勤められた
・スバル社版「スバル」創刊,昭和二一年六月(A5,p32,3.50円)
これはその年に4号まで出る(後藤竹志編集)
これに執筆。新月書房ではなく、スバル社としたようです
(なぜか、「萬国」創刊と同じ月です)
都筑さんは、昭和二一年暮れか、昭和二二年の春、としていました
・「萬国」改題「スバル」の創刊が昭和二二年十一月(十二月表示もある)で、
2巻1号とされ、10冊まで出る(終刊は昭和二四年二月)
・昭和二三年に創刊された「ポケット講談」青灯社(後藤竹志編集長)、に書く (十八歳)
・昭和二四年「毎日読物」阿部主計編集長、に書く
昭和二四年頃、都筑道夫を用いる(十九歳)
スバル社版「スバル」には都筑さんの原点があるのでしょうか。
相変わらずニッチねたですが、
戦争末期に満州からソ連に没収されていたフィルムが東京国立近代美術館フィルムセンターで上映されいていますが、そのうち、現存しないと思われていた角田喜久雄原作の「鍔鳴浪人」を見てきました。(今日が最終上映でした。)
開始早々、侍が斬られ、「約定書」という言葉を吐きながら死んでいくので、ダイイングメッセージ物かと期待されましたが、あまり意味はありませんでした。
主役は坂妻(田村正和、高広、亮三兄弟の父)、沢村国太郎(津川雅彦、長門弘之兄弟の父)で、後年黒沢映画で巨匠となる志村喬がロシア人、上田吉二郎が中国人を怪演していました。
PS.ビデオで映画「月光の囁き」も見ました。江戸川乱歩の世界を現代の高校生に移しかえた傑作で、見逃せません。原作者である喜国先生は今後巨匠と呼ばせていただきたいと思います。
桜様
>岡田時彦は、どうでしょうか、三人の「岡」さんになります。
>アンソロジー、このところ、多く出てきて、しかも、書誌があるのには感謝
>せざるを得ません。
そう言えば、渡辺啓助さん、「偽眼のマドンナ」を岡田時彦名義で発表
しておられるんですね。夕べ桜さんの書きこみ見て、今日は一日「ネメク
モア」を読んでいました。これから、創元推理文庫「名作集Ⅰ」で
「偽眼のマドンナ」を何十年ぶりかで再読するつもりです。
見ました。ちゃんといきさつまで載ってましたね。案外忘れてしまうもので。
『幻影城』を見てしばらく悩んでいたのですが、どうやら島崎さんの『幻影城』でのリストが間違っているのに幻惑されていたようです。『スバル』の創刊号は昭和22年1月ではなく11月が正しいようですね。
つまり『萬国』(昭和21年6月)と萬国新報社の『スバル』(昭和22年11月)の間(昭和22年?)にスバル社の『スバル』が4冊挟まれていたということで、これは島崎リストの1月を11月に修正することによってつじつまが合うんですね(昭和21年7月~12月の可能性はないのでしょうか?)。
あまりややこしいから、自信がなくなってきましたが、こんな答案でいかがでしょうか。>桜様
でも、なぜ昭和22年11月に改めて「創刊号」を出したのでしょうか。
末永さん、見ている文献は同じと思います。
もう少し、この話を続けます。
なぜ、『萬国』改題「スバル」萬国新報社の、創刊号が2巻1号であるのか、
知りたかったのですが、都筑さんの本から推測して、わかりました。
スバル社版「スバル」(1巻1号から4号までか)と「萬国」改題「スバル」についていえば、
・両誌とも、編集・発行人が後藤竹志(本名毅)である
・改題されても、引きついで、2巻1号から、10冊が、昭和24年2月まで刊行された
個人的には、遭遇しながら、何度か逃しています。この改題のものは、雑誌「幻影城」に作品リストが掲載されています。
昭和21年6月でした。毎月出ていたのかはわかりませんが、結構長続きしてますね。
たぶん、私の見ているものと同じでしょうが、『スバル』は昭和22年11月からのようですね。>桜様。
ただ、これが『萬国』の後身というのには驚きました。
ということで、『萬国』の創刊を調べようと思ったのですが、手許の資料には載っていませんでした。何度か見たことはあるのですが、調べるとなると案外わからないもので。
カストリ雑誌の改題関係なんて、今調べるのは大変ですね。カストリじゃないのですが、『夫婦生活』の前身が『話』というのも、今度初めて知りました。
相変わらずワケのわからない話で恐縮です。
岩堀さん、岡田時彦は、どうでしょうか、三人の「岡」さんになります。アンソロジー、このところ、多く出てきて、しかも、書誌があるのには感謝せざるを得ません。
都筑道夫『推理作家の出来るまで』上巻を読んでいます。
個人的には、都筑さんが、スバル社版の雑誌「スバル」にかかれていたことを知り、いままで、この雑誌の存在が知られていなかったので、勉強になりました。
・4冊、でているらしい
・何を書かれたかは明らかにされていないようです
恐らく、創刊は、昭和二二年でしょうか、そのように思われます。
岡田鯱彦さん
石井さんの刺激を受けて最近桜木町の神奈川県立図書館に時々行ってい
ます。先日、国書刊行会の探偵クラブ叢書、岡田鯱彦「薫大将と匂宮」
借りました。長年の宿願だった「噴火口上の殺人」読みたかったのです。
期待通りでしたが、本書には、他に表題作と「妖鬼の呪言」が収録されて
います。再読の「薫大将」が岡田鯱彦の代表作であるところは論を待たない
ところですが、「妖鬼」は、それほどの作品とは思えなくなってきました。
初読みは桜さんお持ちの昭和29年4月「探偵実話特別増刊号 現代探偵
小説名作全集」です。お告げの言葉など非常に印象に残っていたので、
何十年後に、あるアンソロジー文庫本で再読したのですが意外に平凡な
印象でした。今回は3読目なのですが、やはり印象変わらずです。
こちらの読み方が浅いのかなあと悩んだりして…。諸賢のご意見賜りたし。
岡村雄輔さん
本格推理マガジン「絢爛たる殺人」読了。冒頭の岡村雄輔「ミデアンの井戸の
七人の娘」が印象的でした。途中までは、「こりゃいかん、まるでミニ小栗、
ミニ黒死館ではないか」と思っていたのですが、真相解明では大いに感服しま
した。真犯人とトリックが密接不可分という着想がすばらしいと思います。
巻末の芦辺さんの解説でも、発表当時「小栗虫太郎を思わせる」という評が
多かったそうですが、そういう印象の為に、岡村さんは大いに損をしているの
ではないかと思います。「黒死館」的雰囲気を設定したかったのはよくわかり
ますが、岡村雄輔独自のカラーをもっと出していたら評価はずっと高かったの
ではないかと愚考致しますが、いかがでしょうか。
なんにしても、「紅鱒館の惨劇」是が非でも読みたくなってきました。
越沼さん御注文ありがとうございます。喜んでいただいて幸いです。しかし奥付を見ていただくとわかるとおり、出してからもう何年もかかってあんまり売れないのですよ。ようやくあと20冊を切るところまでこぎ着けました。(もっともほとんどミステリ関係ではつきあいがなく、ホームズ関係のみで売っていましたが)
友人はコミケにもっていけば売れるぞ、とはいってくれましたが、また調子に乗って再版して在庫を抱え込むのもナンだなあ、と思っております。いかがでしょうか。御意見をお聞かせ下さい。
昨日は、以前、目録で出ていた、新刊の(?)佐左木俊郎『熊の出る開墾地』があたらなかったので、探していましたが、
新潮文庫『熊の出る開墾地』昭和15.9.10発行、昭和16.9.10四刷
を入手。千円。あとがきでは、死後、
『黒い地帯』『熊の出る開墾地』『都会地図の膨脹』の短編集、3著作集から、
14編を選んだ
ということです。
佐左木俊郎は、ささき としろう、ではなく、ささき としお(を)
と読むようです。1900年生まれ、1933年死去。
もうひとつの文献があることに気付いて、その『島田一男読本』昭和32年8月、「別冊宝石」をみました。そのなかの座談会は、島田(五十歳)、中島(四十歳)、黒部(不明)によりおこなわれて、デビュー10年ということです。
1「落葉の譜」『遼東新報』懸賞入選 大連一中の三年生 十八歳か
2「その朝の実朝」雑誌「大陸事情」掲載 大連市役所勤務 二二歳か
については、座談会ではのべられておらず、山村さんの文献だけに掲載されていることになります。
3「叡(右側がない)親王殺人事件」『満州日報』掲載 二四歳以後
叡(右側がない)には永という字がいままで置かれていた
4「死人の丘殺人事件」『満州日報』掲載 二四歳以後
3は、山村さんも上げていました
4番目は、山前さんが文庫の解説で書かれていました。
これら2作品は、座談会の「書きはじめた動機」で、題名があげられていましたので、これを参考にされたように考えられます。
ただし、詳しく言えば、
3は、『満州日報』に、二十回連載
4は、「死人の丘殺人事件」ではなく、「死人丘事件(クウレンカン)」で、
『満州日報』に、三十回連載
であり、いずれも、昭和10年のころ(二八歳)でした。デビューまで、空白の期間があることになります。
私もフツーの話題を。No.1113の書き込みの平山氏から昨日『明智小五郎年代学』が届きました。資料としても、読物としてもよくできていて、コリャ、ミステリ者との挨拶がわりにもっと注文しとけばよかった、という小冊子です。これをネタに話題がいっぱい作れますワ。
| Powered by T-Note Ver.3.20 |